これから法人登記するという人は、登記住所が必要になりますが、バーチャルオフィスを登記住所とする場合、違法性や注意点はないのでしょうか?
実は、注意していないと、知らずに違法なことをしてしまうケースがあるのです。
本記事ではバーチャルオフィスを登記住所にする際の詳細について解説しているので、注意点などを理解した上で安全に登記しましょう。
バーチャルオフィスの住所で法人登記は可能なのか?
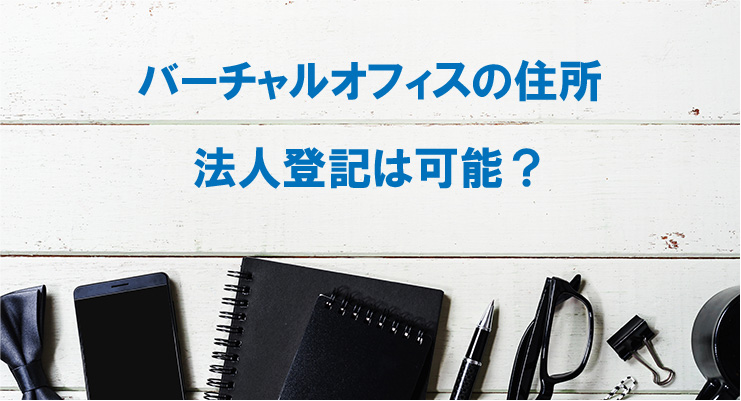
そもそもの話しですが結論からいうと、バーチャルオフィスでの法人登記は可能です。
リモートワークや出張サービス、ネットを使った事業などが増えたことで、「バーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる」と法解釈が明文化されています。
しかし、注意点を理解しておかないと、違法な使い方をしてトラブルに巻き込まれたり、融資を受けられない場合があります。
法人としての融資や銀行口座開設も可能?
法人設立をした際に、なぜ住所登記が必要なのかというと、
- 法人の信用度を維持するため
- 取引先が安心して取引できるため
そのため、バーチャルオフィスの住所が不自然な場所にあったり、
外観が会社のイメージを下げる場合、企業として信用してもらえない可能性がでてきます。
また、バーチャルオフィスは詐欺など悪用にも利用されやすいため、事業内容がきっちりしていないと、 法人名義で口座開設すらできないケースがあります。
融資に関しては、日本政策金融公庫は、登記住所がバーチャルオフィスであっても融資を受けられますが、金融機関によってはバーチャルオフィスという時点で断られる場合があります。
ただ、融資を受ける上で大事なのは、事業内容や将来性なので、どういう事業で、どういう可能性があるのかをしっかりと説明できるように準備しておくことが大切です。
バーチャルオフィスの登記利用は違法なの?ほんとに大丈夫?

バーチャルオフィスの登記利用に関する違法性については、注意が必要です。
事業形態によっては、バーチャルオフィスが認可されないからです。
たとえば、
・人材派遣業
・不動産
・建設業
・古物商
・弁護士や司法書士などの士業
これらは、実際に活動している住所が必要となります。
古物商は、個人の副業などでも行われていますが、「盗品などの売買防止とすみやかな発見」という目的により、バーチャルオフィスは登記住所として認められていないのです。
バーチャルオフィスで登記する際のメリットとデメリット

メリットとしては、、
バーチャルオフィスで登記する際のメリットとしては、、
- 初期費用を抑えることができる。
- 法人設立までの期間を短縮できる。
- 都心の一等地を住所に選ぶこともできる。
- 固定電話やFAXの導入も簡単にできる。
- 自分の住所を公開しなくてもいい。
実際に賃貸を借りようと思うと、時間もお金もかかりますが、バーチャルオフィスは数日で利用することができ、費用も大幅に下げることができます。
バーチャルオフィスによって費用やサービス内容は異なりますが、毎月のランニングコストが無料〜数千円で利用することができます。
それでいて、電話やFAX転送もしてくれるので、設備投資にかかる費用もカットできます。
一方で、物件契約する場合、保証金や敷金、仲介手数料、配線工事や内装工事など、初期費用だけでも数十万円かかりますし、毎月数万円〜数十万円の経費もかかります。
また、名刺に一等地の住所を記載することで、会社の信用に繋げることもできます。
今は「特定商取引法」によって、インターネットで商品を販売する場合でも、販売者の氏名、住所、電話番号の表記が義務となっています。
「特定商取引法に基づく表記」が必須となります。
住所や電話番号のような運営者の連絡先の表示が義務となってきます。
とはいえ、自分の自宅住所を記載するのは、防犯上の理由から避けたい方も多いことでしょう。
そういう場合にもバーチャルオフィスは便利です。
デメリットとしては、、
- 融資の際のハードルになる場合がある。
- バーチャルオフィスと知られることで、逆に信用が下がることもある。
- 仕事や会議場所を別で確保する必要がある。
- 郵便物の転送に時間がかかる。
が挙げられます。
郵便物の転送サービスはありますが、一度バーチャルオフィスに届いてから、自宅などに転送となるため、急ぎの書類の場合は、自宅に直接送ってもらうように手配する必要があります。
また、商談なども別の場所を確保する必要があるため、別の経費がかかる場合もあります。
取引先の住所を調べる企業も多いため、バーチャルオフィスと知られることで、逆に信用が下がるケースもありますが、事業内容と対応がしっかりしていれば、バーチャルオフィスだから取引を断られるということは考えにくいです。
⇒バーチャルオフィスの詳細を見る!
法人登記の時にバーチャルオフィスを選ぶ際のポイント
~違法営業のバーチャルオフィスを避ける~

契約するのは避けたい違法性のあるバーチャルオフィスについても知っておきましょう。
バーチャルオフィスも会社や人が運営しているものであり、自分が利用するバーチャルオフィスそのものが違法な運営をしている、またはトラブルのリスクがある場合もあります。
本人確認や審査がないバーチャルオフィスや「即日OK」などの審査が緩いというバーチャルオフィスの場合も、トラブルのリスクが高いです。
バーチャルオフィスの運営側としても、「この住所の会社が詐欺をした」と社会に出ることは避けたいものですし、信用を担保出来る会社と契約したいですね。
まともなバーチャルオフィスは、トラブルの可能性がある会社との契約を避けるため、審査基準なども判断材料として参考にしましょう。
バーチャルオフィス利用での登記費用の目安

バーチャルオフィスで登記する場合の、費用の目安について説明します。
自分で登記する場合と、司法書士などの専門家に依頼する場合で、かかる費用が異なります。
また、電子認証で行うのか、紙の定款で行うのかでも費用が変わります。
電子認証の場合、紙の定款の際に貼らなくてはいけない収入印紙が不要になりますが、
パソコンソフト、カードリーダー、電子認証カードの作成などの費用がかかります。
そのため、電子認証での登記を専門家に依頼することが多いです。
個人で法人登記する場合の費用の目安としては、
- 収入印紙 40,000円
- 定款認証 50,000円
- 謄本交付料 2,000円
- 登録免許税 150,000円
- 合計 242,000円
専門家に電子認証での登記を依頼する場合、
- 定款認証 50,000円
- 謄本交付料 300円
- 登録免許税 150,000円
- 専門家手数料 +α(相場は50,000〜200,000円)
- 合計 250,300〜
専門家に電子定款を依頼した場合、収入印紙代がかからないため、依頼の際の手数料が収入印紙代と変わらない場合は、自分でしても専門家に依頼しても必要な費用は大きくは変わりません。
そのため、専門家に依頼した方が、時間や手間がかからず、手続きの不備などで戸惑う心配もないといえるでしょう。
バーチャルオフィスで法人登記する時の手続きの流れ
さいごに、バーチャルオフィスで法人登記をする時の流れですが、
- ①会社名を決める。
- ②印鑑の作成。
- ③バーチャルオフィスの審査を受け、契約する。
- ④定款の作成と認証。
- ⑤資本金の入金。
- ⑥登記書類を作成する。
- ⑦本社所在地の法務局で申請する。
- ⑧登記後に、バーチャルオフィスに連絡し登記した旨を伝える。
自分で登記することもできますが、「難しい」「時間がない」という方は、司法書士の方にお願いすることで、登記に必要な手続きをお願いすることもできます。
まとめ

バーチャルオフィスを登記住所にすることはできますが、事業内容によっては利用できないので、登記前に確認しておきましょう。
バーチャルオフィスは、初期費用を抑えることができるため、これから起業する人にとって、とても助かるサービスといえます。
メリット、デメリットを理解し、上手にバーチャルオフィスを活用していきましょう。





